さよならは始まりの薬膳
心と体を整える保存版レシピ
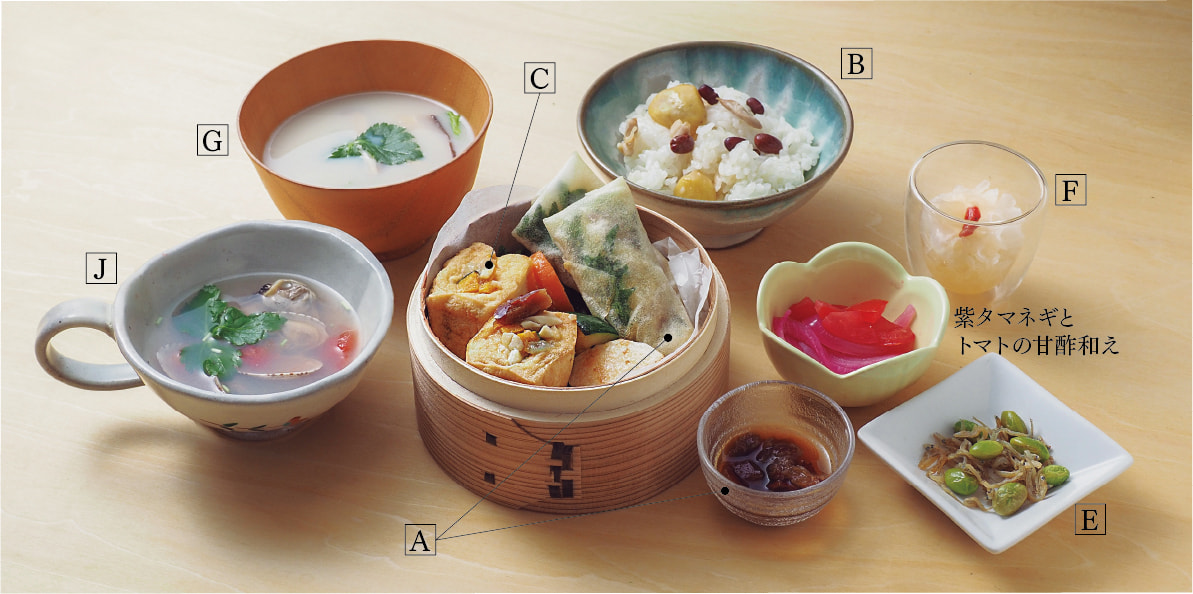
今回は皆様の健やかな日々を支える「1週間の薬膳レシピ」をお届けします。晩夏から初秋にかけての季節に寄り添いながらも、一年を通して活用できる「整える薬膳」の知恵が詰まっています。
「さよなら」は、新たな「はじまり」でもあります。この投稿を通じて、薬膳が皆様の暮らしに寄り添い、健やかな毎日を送るための一助となれたなら幸いです。
私が提唱している、〝多種多品目の食材をバランスよく食べることで健康寿命を延ばす〟を表現した作り置き・スープ足しレシピを、保存版として1週間分にまとめました。
1週間の終わりとはじまりを整える薬膳ごはん
月曜日:肺を整える
秋の乾燥に、肺を潤す。
A:豆苗の薬膳春巻き&棗のソース
火曜日:心を安定
温かさで呼吸を整える。
B: 鶏とキノコの炊き込みご飯
C: 棗と海老の厚揚げ蒸し
水曜日:胃を整える
胃を温め、潤い守る。
D:長芋とズッキーニのゴマ油炒め
E:枝豆とじゃこの炒め物
木曜日:脾と肝を守る
とろみで喉と肺を保護。
F:白キクラゲと桃のジャム和え
G:豆乳のとろろスープ
金曜日:腎を補う
体を温め、咳を予防。
H:ひじきとキノコの炒め物
I : 小豆とかぼちゃの炊いたん
土・日曜日:腎と肝を休める
滋養で潤い。
J:アサリとトマトのスープ(三つ葉添え)
K:ほうれん草とコーン・ベーコンのソテー

心をゆるめる
A:基本の棗(ナツメ)ソース
◆ 材料(2人分)◆
・乾燥棗(種なしが便利)・・・・・・・・大3~5個(大きさによりお好みで量を調整してください)
・水・・・・・・・・200cc程度
・生姜のすりおろし・・・・・・・・小さじ1/2(風味付け、お好みで)
◆ つくり方 ◆
① 乾燥棗を軽く洗い、種を取り除いて細かく刻む。
② 鍋に刻んだ棗と水を入れて中火にかけ、棗が柔らかくなるまで10~15分煮込む。(水が少なくなったら適宜足してください)
③ 生姜を②とあわせて焦げ付かないよう煮詰める。

春巻きの具
(豆苗、大葉、紫タマネギ、人参、サラダチキン)
ソースアレンジ2種
ピリカラ風 :基本の棗ソースを煮込む際にニンニクや鷹の爪を入れる。
エスニック風:基本の棗ソースに市販のスイートチリソースを混ぜる。
疲労回復・貧血予防に良い食材と、胃腸の働きを助ける食材の組み合わせ
B:鶏とキノコの炊き込みご飯
◆ 材料(2人分)◆
・米・・・・・・・・1合(もち米を小さじ2ほど混ぜる)
・鶏もも肉・・・・・・・・100g(こま切れ)
・水煮のむき栗・・・・・・・・お好みの量(今回は50g)
・乾燥棗(種なしが便利)・・・・・・・・2~3個
・小豆(水煮、サラダ小豆でも可)・・・・・・・・・適量
・お好みのキノコ類・・・・・・・・適量(今回はマイタケを50g使用)
・人参・・・・・・・・適量(千切り)
・生姜の薄切り・・・・・・・・1枚(千切り)
・水・・・・・・・・炊飯器の2合の目盛りに合わせる
☆醬油・・・・・・・・大さじ1
☆みりん・・・・・・・・大さじ1/2
☆酒・・・・・・・・大さじ1/2
☆和風顆粒だし・・・・・・・・小さじ1/2
◆ つくり方 ◆
下準備:米・もち米は洗って30分ほど浸水。 鶏もも肉はこま切れ。キノコ類は石づきを外しほぐしておく。人参、生姜は千切り。棗は洗っておく。
① 炊飯器に米・調味料(☆)・水(2合の目盛りまで)、むき栗・小豆や下準備しておいた材料を入れ炊飯する。
② 炊きあがったら軽く混ぜる。
身体の津液を増やし潤いチャージ
F:白キクラゲと桃のジャム和え
◆ 材料とつくり方(2人分) ◆
・乾燥白キクラゲ・・・・・・・・10g
・桃ジャム(市販のものでOK)・・・・・・・・大さじ2~3(お好みの甘さで調整)
・水・・・・・・・・300cc
・クコの実・・・・・・・・小さじ1
下準備:乾燥白キクラゲをボウルに入れ、たっぷりの水に30分~1時間ほど浸して戻す。石づきを包丁で取り除き、食べやすい大ききさに手でちぎる。細かくちぎるほどとろみが出やすくなります。
① 鍋に水と戻した白キクラゲを入れ、中火にかける。沸騰したら弱火にし、蓋をして30分~1時間ほど、白キクラゲが半透明になりとろみが出るまで煮詰める。(水が少なくなりすぎたら、適宜足してください)
② 白キクラゲが柔らかくなったら火を止め、粗熱をとる。
③ 粗熱がとれたら、桃ジャムを加えてよく混ぜ合わせる。
④ 器に盛り付け、クコの実を散らして出来上がり。
あとひと踏ん張りを支える
G:豆乳のとろろスープ
◆ 材料(2人分)◆
・すりおろした長芋・・・・・・・・100g
・マイタケ・・・・・・・・お好みの量
・三つ葉・・・・・・・・お好みの量
・豆乳・・・・・・・・200cc
・あご出汁(顆粒でOK)・・・・・・・・200cc
・味噌・・・・・・・・大さじ1(お好みで調整)
◆ つくり方 ◆
① マイタケは石づきを落としてほぐしておく。
三つ葉は、葉と茎で分け茎は刻んでおく。
② 鍋にあご出汁と味噌を入れ、中火にかけ沸騰させ、マイタケを加えて煮る。
③ 一旦火を止め、豆乳を加えて混ぜる。
④ すりおろした長芋を入れる。
⑤ 器に盛り付け、三つ葉を入れる。(お好みでネギや七味唐辛子を散らす)
監修/食と暮らし方のエコノミスト
岩本 節子 Setsuko Iwamoto
処方箋堂ふなしち 代表 国際中医薬膳管理師 予防薬膳専門家
多種多品目の食材をバランスよく食べることで健康寿命を延ばす、家族のための予防薬膳教室を、地元である大東市住道(大阪)で開催。
大和当帰の栽培、薬膳素材を使ったスープや当帰の調味料などの開発を行っている。


